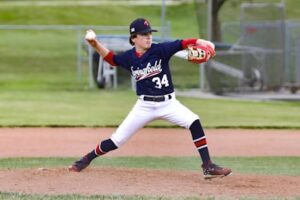ここ数年はSNSの発達でトレーニング方法や技術練習の動画がたくさん出回っています。元プロ野球選手や元甲子園出場経験のある人、理学療法士やアスレティックトレーナーなどなど、、。
特に、InstagramとTikTokは短時間動画で説明されているため、見やすく参考にしやすいと思います。
ただ、そのような動画を鵜呑みにしてはいけないと私は思います。
自分は動画を上げてないくせに何を言っている
じゃあ、何をやればいいんだ
なんて思われているのではないかと思います。
確かに、私自身は「パフォーマンス向上のための動画」や「球速up、打撃飛距離向上のための動画」などは本ブログでは取り上げていません。
それは、そもそも私自身が「理学療法士」であり「競技力向上の専門家」ではないことが理由です。
ただ、理学療法士としてや野球部のトレーナーとして活動している上で、少なくとも選手や指導者、保護者の方よりは人間の身体に関する知識はあるつもりです。
そして、今現在は「S&Cコーチ」になるために勉強をしているため、トレーニングに関する知識も多少なりともあります。もちろん、まだその道の専門家になってわけではないので「ストレングス」の分野においてはしゃしゃり出る真似はしませんが。
少し話が脱線してしまいましたので戻します。野球に関する情報がありふれている現在、どの情報を有効活用すれば良いかに迷うことが多いと思います。
今回は「理学療法士」という立場から、野球のパフォーマンス向上に必要な考え方を述べていきます!
本日のお品書き
情報は一例であり、あなたに当てはまるものではない

まず、大前提として考えて欲しいのは動画などで挙げられているエクササイズが「見ているあなたには当てはまるとは限らない」ということです。
例えば「これをやれば球速上がります!」的な動画。これはやる人の年齢や野球歴、持ち合わせている体力に左右されます。また、どのような選手を対象にした動画なのかもわかりません。
基本的に動画として挙げられているのは、一選手に対してもしくは、自分自身の競技経験として行った成功例の方法が挙げられています。
つまり、見る側の個人にパーソナライズされた方法ではないため、効果的かつ効率的ではないと考えられます。
もう一つ例を上げてみます。「これで野球肩が治ります!」みたいな動画。んなわけないでしょうが、と私は思います。
それやって治ったらリハビリがいらんでしょう、なんで相手の機能状態を分からずに治るなんて言えるのか。投球時に肩が痛い理由は様々なのに、動画のことをやってよくなるなんて投球障害を甘くみて、変な夢を持たせるな!と。
なんで痛いのか、何が原因で痛いのかをはっきりしない状態であれこれやってると、原因によっては痛みが慢性化する可能性のあるものもあります。
まずは病院に受診して原因を知り、適切なリハビリを受けるのが先決です!怪我をしたり、痛みがあればまずは医療機関を受診です。整骨院やカイロではないです!まずはいわゆる病院を受診しましょう!
じゃあ、パフォーマンスを上げるには?
「パフォーマンスをあげる」と一言で言っても複数の種類があるかと思います。
- 球速、スイングスピード、走力などを今よりも上げる。(痛みはなく、今ある能力をさらに上げたい)
- 怪我による痛みで出力をフルまで上げられない(痛みがあり十分にプレーできない)
- 術後復帰はしたものの、以前よりも動きが鈍い(怪我で離脱した期間が長く、以前ほどのプレーができない)
大きく分類するとこんな感じでしょうか。それぞれのケースについて、私なりにパフォーマンスアップに必要な要素を解説していきます。
痛みはなく、今ある能力をさらに上げたい
多くの選手はこちらに該当するのではないかと思います。こちらに関しては私の専門領域ではないので、とやかくいうことはありません。
が!しかーし!1つ物申したいことで言えば、よく動画で出回っている「ファンクショナル」なるトレーニング。実際の投球動作に重りを用いてトレーニングしたり、シャフトを担いでやってみたり、、。
怪我します、やめてください。一時的に投げやすくなるのかもしれませんが、長期的に効果はでづらいでしょう。
私が競技力向上、パフォーマンスを上げるために必要と思う考え方は以下の4点です。
- スクワットやデッドリフト、懸垂などのベーシックなトレーニングを長期的に取り組み自身の体力を向上させること。
- トレーニングはあくまでも体力強化のための手段であり、練習とは別という認識を持つこと。
- トレーニングの効果が出るのは一定期間を要し、継続する必要あること。
- トレーニングにより効果が現れるのではなく、トレーニングをして体力が向上し、それを競技練習で自分の技術に落とし込むことで競技能力が向上すること。
これらを意識した上で、取り組むことにより競技力向上への一歩を踏み出せると考えます。逆に、無理なトレーニングや練習は怪我をするリスクが上がり、パフォーマンスダウンに繋がりかねないのでご注意ください。
痛みがあり十分にプレーできない
2つ目は怪我により痛みがあり、十分なパフォーマンス発揮ができないケースです。
よくあるのは
練習を休むとレギュラーから外されるから
怪我をしたと言うと、いい顔をされないと思うから
こういう選手って結構いるんです。特に中高生は多い印象です。けど、よく考えてみてください。
怪我を隠して十分なパフォーマンスが発揮できないまま、練習や試合に臨んでる方が周りとの差がつき、レギュラーから遠のきませんか?
怪我を隠して大事な場面、チャンスの局面で本来のプレーができなくて負けた時に、自分に後悔しチームにも迷惑がかかると思いませんか?
そうならないためにも、早期に対応し早期に復帰することが大切なのです。痛みは慢性化すればするほど改善しづらくなります。加えて、痛みをかばう動作が身体に定着すると、効率の悪い動作となりパフォーマンスは落ちます。
痛みや違和感がある場合は、早期に医療機関を受診し診断、適切なリハビリを受ける必要があります。リハビリを受ける中で、自分の身体に足りない要素を改善し、十分なパフォーマンスを発揮できる身体で競技に復帰できるようにしましょう!
大事なのは段階的な復帰と再発予防に努めることです。その手段として
- リハビリに定期的に通院する
- 長期的目標をセラピストと考え設定する
- 設定した目標を指導者に伝え、段階的に競技に復帰できる環境づくりをする
- リハビリの中で指導されたメニューは、自身のコンディショニング内容に取り入れる
- 何かわからないこと、自分の体で改善したいことがあれば遠慮せずに聞く
リハビリに関しては、正直受診する医療機関や所属するセラピストに左右されることがあります。そのため、可能な限り事前にリサーチした上で受診することをオススメします!
怪我で離脱した期間が長く、以前ほどのプレーができない
最後は怪我による離脱期間が長く、パフォーマンスが怪我前に追いつかないケースです。
膝前十字靭帯損傷の手術や、トミージョン手術の後は復帰までに長い期間を要します。場所によっては手術後のフォローが不十分だと感じる医療機関もあります。
半年からそれ以上の期間を競技から離れる、もしくは簡易的な練習にしか入れないとなるとパフォーマンスは下がります。
競技離脱時間が長ければ、試合感や緊張感の中でのプレーや球際の感覚など、様々な感覚とそれに伴うからの動きは低下するものです。
そこから復帰していくには積極的に参加していくことはもちろん、自分の身体の機能で落ちている機能を再教育していく必要があるのです。方法としては
- 理学療法士やアスレティックトレーナーに身体の評価をしてもらう
- 機能に異常がなければ、補強を入れながら競技練習に打ち込む時間を増やしていく
上記2点が特に必要なことになると考えます。術後は復帰過程の中で必ずと言っていいほど、身体の左右差や、それに伴う姿勢制御機能と筋力低下が見受けられます。
自分だけで機能低下を判別することは、まず難しいので専門家を頼るようにしましょう!
大前提として競技パフォーマンスは競技練習でしか向上しない!

ここまで、あれこれぼやかせてもらいましたが競技パフォーマンスを上げるうえで一番大事なのは、競技練習だと言うことを忘れてはいけません。
いくら補強をしようが、身体の動きを変えるドリルをやろうがすぐに競技パフォーマンスが変わるわけではありません。
自分の身体に必要なことを長期的に取り組み、変化が出た体力で競技練習に打ち込むことで、自分自身の技術に反映された時、結果としてパフォーマンス向上につながるのです!
これをやれば良い、なんてものは存在しないのです。その時の自分の身体に何が必要で、その後にどれだけ競技練習できるかが大事なんです!

まとめ
- SNS上の技術やトレーニング動画は鵜呑みにしない
- 動画は個人に向けたものではないため、見る側に効果が当てはまるものではない
- 痛みによるパフォーマンス低下は、まず医療機関受診を!
- 競技パフォーマンスを上げるには、競技練習が不可欠!
自分がどう行動を取るかで、未来の自分は大きく変わります。まずは一歩踏み出してみましょう!