野球肩や野球肘のリハビリに関わっている際に「投球動作指導」というオーダーを医師から受けたことがあると思います。
投球動作指導ってどこまで踏み込んでいいか分からない
投球動作のどこから着手していいか分からない
そんな悩みを持ったことありませんか?
私は入職してから半年のタイミングで投球障害の患者さんを初めて治療しました。当初は何をしたらいいのか正直わかりませんでした。
「障害予防の視点からみた投球動作の型」みたいなものは文献で出回っているため、そこから逸脱してる部分を修正すればいいのか、なんて漠然と考えていたのを今でも覚えています。
でもそれでは、選手の長所を消してしまう可能性やパフォーマンスを下げてしまう可能性が出てきます。リハビリのせいで投球パフォーマンスが下がった!なんて言われたくないですよね。それに、型に沿って考えると動きだけにとらわれてしまいます。必要なのは機能そのものが改善することで、動作にプラスの影響を及ばすことです。
私は理学療法士としてスポーツ整形外科の領域に関わって7年を迎えます。その中でも特に「野球」の分野に関わり続け、院内でのリハビリ業務と高校野球部のメディカルスタッフとして活動しています。加えて、野球肘検診を毎年行い、その中で投球障害リスクを減らすためのコンディショニング指導の活動も行っています。
この記事は基本的に同業者(投球障害肩・肘に関わる新人理学療法士や新人AT)の方々に向けて書いています!記事を読み終える時には、投球動作指導の時の考え方のイメージが掴めます。治療の一歩をぜひ踏み出してもらえれば、と思いす!
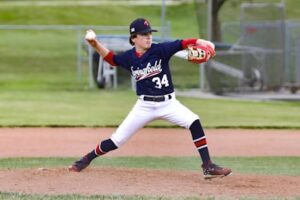
本日のお品書き
投球フォームそのものを指導しようとしないことが大切!
いやいや、「リハビリで投球フォーム指導をしてください」ってきてるのに指導しようとしないってどういうことだよ!ってツッコミが聞こえてきます。おっしゃる通りです。
ここで私が伝えたいのは、投球フォームそのものを指導しようとしなくても、選手の身体機能が変わればそれに合わせて投球フォームは変わるものだ、と言いたいんです。
さらに言えば、投球フォームを選手が持ち合わせている個性だとします。なるべくその個性を消さずに機能改善を図った結果として、症状が改善すればそれがいいと思うのです。
なので、投球フォーム指導をしようとする前に「その選手のどこの機能が落ちているのか」を評価できるようになりましょう!例えば、肘下がりのフォームの選手であれば「肘を上げるようにしよう!」と指導するのではなく、肩甲骨が下制していないかを確認。もしくは、肩甲骨の上方回旋や胸椎の側屈可動性を改善する、などを行うことで結果的に肘が上がりやすい状態を作ることがベストだと考えます。
これはあくまでも「リハビリテーションのなかでの投球フォーム指導」です。パフォーマンス(球速、キレなど)を上げるための投球フォームではありません。大切なのは、選手自身がいかにスムーズに動作ができるか、怪我のリスクを最小限に抑えた中で投球ができるか、なのです。

フォームそのものの修正を考えない分、機能改善に集中できる!
フォーム自体の修正をしないことで、自分自身がアプローチする点に集中できて、そこに時間をかけることができます。時間をかけれるということは、より詳細に機能評価することができます。より治療にかける時間が増えます。よりエクササイズに使う時間が増えます。などなど
「機能改善」にタスクを絞ることにより、こんなにもメリットがあるのです。やらない手はないですよね!もちろん、大前提は「選手の痛みを取ること、障害リスクを低減する事」のため、ただの機能改善ではないです。投球フォームや機能不全からくる「身体への機械的ストレス」の機能改善を行うことが大切です!
「肩甲胸郭関節の可動域改善」で肘の痛みが減ることを例に
実際のケースを例に考えるともっとわかりやすいかと思います。
例えば、選手Aが「最大外旋位(MER)で肘の内側に痛みが出る」という症状でリハビリに来たとします。肘内側の痛みがMER肢位で痛みが出る→胸椎の伸展を促すと痛みが消えることを確認。
だとすればフォーム修正をせずとも、肩甲胸郭機能を改善するだけで症状の改善を見込めますよね。加えて、肩甲胸郭機能向上による肘への外反ストレス軽減効果から、今後の投球による障害リスクの低減にもなります。
同じように、前腕の回内制限を改善することや上腕の内旋可動域の改善、僧帽筋や前鋸筋などの固定筋の賦活で症状が改善するケースって多いです。
理学療法士は投球フォームの専門家ではなく、リハビリの専門家!
もちろん、投球フォームから機能障害を考える必要性はあります。が、投球フォームそのものをよくする専門家ではありません。それを生業にしている方々からすれば知識は少ないでしょう。
それに、障害リスクの低い投球フォーム=投球パフォーマンスが高いフォームとはならないのが現実です。だとすれば「絶対的にこれは怪我するだろう!」みたいな投球フォームでない限り、あえて投球フォーム指導をすることを第一選択にする必要はないと思うのです。
自分たちが専門としているリハビリテーションの領域。身体機能の改善を中心にプログラムを組み、その中で症状改善を図る、それが結果的に投球フォームにプラスの影響を与えるというのが理想的だと思うのです。
「理学療法士としての強みや自分の得意な分野をフル活用して、選手の機能回復の触媒となれるように努力していく」ということを私は常に考えながら、選手たちと関わっています。
まずは自分のできることに全力を尽くしてみては?
いまいち自信や根拠が持てないことに取り組む必要はありません。もちろん、それができるように努力をすることは大事です。でも、目の前の選手に自分が100%でできないことはやるべきではないと私は思います。選手の時間やお金をもらってやっていることなので。
だったら、まずは自分が100%根拠と自信を持って提供できることをやってみましょう!








