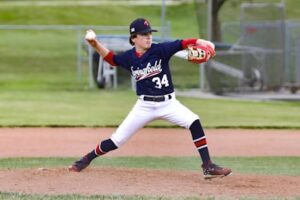突然ですが、皆さんは「アームケア」という言葉を知っていますか。とは言う私もつい最近までは知りませんでした。長年野球部のトレーナー、理学療法士として働いてたのに恥ずかしい限りです、、
とはいえ、やっていること自体は同じことをやってきているので、自分自身がやっていることは間違ってはいないんだな、と再確認できたのは良かったです。
この「アームケア」はメジャーリーグや日本のプロ野球のなかでもメディカル系トレーナーなどが選手と一緒になって行っていたり、装着する測定器によりデータが取得できるArmcareという機械がありハイレベルな環境ではメジャーになりつつあります。と言うより、それが当たり前になっています。
しかし、言葉自体があまり浸透していないこともあり言われた時にパッと内容が思い浮かばないと思います。「アームケアだから腕のマッサージとか電気かけるのかな」とか、中には「中高年のむくみ予防とか日焼け予防かな」なんて人もいるとも思います。
でも実際にはとても重要な取り組みなんです!野球をやっているならやらなきゃ損!というかやらなきゃいけないことなんです!
今回はそんな「アームケア」についてを理学療法士、野球部トレーナーの目線から徹底解説していきます!
この記事を読むことで、選手自身や指導者、保護者の方々が「アームケア」の重要性を理解することができ
今までは知らなかったけどやっていこう!
「アームケア」をやらないと確実に損をする!今すぐにでも実践しよう!
そう思うような記事になっています。ぜひ最後まで読んでください!
本日のお品書き
野球における「アームケア」とは投球障害の予防効果を期待した取り組み
そもそもアームケアとは何なのか
アームケアとは、投球障害(野球肘や野球肩)のリスクを低減するために身体機能を調整することです。(具体的な定義はわかりませんので私の見解です。)
「アームケア」と書いているため、腕のマッサージやストレッチ、電気治療などを連想しやすいですがやることはもっと複雑です。治療を受けるというよりもエクササイズやモビリティドリルなどを選手自身が行いながら、リコンディショニングを図るというものです。
つまり、選手が何かをしてもらうのではなく選手自身が自身の身体を使いながら調整するのです。対象となる場所は腕に限らず、首から足先に至るまで全てと捉えます。
アームケアを実践するには
練習後や試合後に運動し終えた身体には左右差やそれに伴う筋機能不全が出現しています。肩甲骨の位置関係が崩れていたり、肩周りの筋出力が低下していたり、骨盤の前傾や後傾が過度になっていたりなどなど、、
まずはそのような姿勢や関節可動域、筋機能状態などを把握する必要があります。これを選手が自分自身で行うのは困難です。そのため、基本的にはトレーナーと選手がペアとなって行います。
私は次のようなステップを踏んで行っていきます。
選手の身体機能を評価する
・肩甲骨のアライメント(左右差、前傾、下制など)
・骨盤のアライメント(左右のフレア、前傾・後傾)
・可動域評価(肩甲胸郭、肘、体幹、股関節、足関節)
・柔軟性評価(上肢から体幹・下肢まで)
・筋機能評価(回旋筋腱板、肩甲骨固定筋、前腕回内・屈筋)
・スクリーニングで得たデータを選手に共有し、選手自身にも現状を把握してもらう
・アライメントや可動域を改善するためにストレッチやモビリティドリルを選択する
・アライメント、可動域修正後に低下している筋機能を賦活するようなエクササイズを組み込む
・エクササイズ実施時の感覚や効果に合わせて実施方法の修正、変更を行いながら進める
・方法に合わせて、目的と実施するケースの説明を行い選手自身が後からでも行えるように指導する
野球でなぜアームケアを推奨するのか
日々の練習や試合における身体各所の疲労軽減
野球というスポーツは基本的に片側だけの動作が多い競技になります。スイッチヒッターでない限り左右どちらかの打席でのスイングになります。右投げの選手が投げる際も、今日は調子悪いから左投げにしようなんてことも基本的にはあり得ないわけです。
右投げであれば右肩、右肘へのストレス量は左に比べて圧倒的に多くなります。右打ちの打者が振込みをすれば左腰のストレスは増えます。
全身運動をしている競技ではありますが、ストレスが集中しやすい部位は存在します。その積み重ねが「障害」を引き起こしてしまうのです。
そのストレス=「身体組織の疲労」を取り除き、翌日までになるべくフレッシュな状態で練習に望むことが重要なのです。その理由は次の項目につながります。
無意識下での外的ストレス増強による障害発生リスクの低減
日々のケアで自らの身体ストレスが緩和されていないと、姿勢要素や筋出力が低下している状態で翌日の練習や試合に臨まなければなりません。
練習では同じ動作を反復するような技術練習が、試合では練習とは違う緊張や力みが生じるケースが多くなります。いつもと同様に自分がやっているつもりでも、身体は実際の動きとは僅かに異なるものです。
例えば、肩甲骨が下制位(反対側に比べて下がっている状態)を呈した状態で投球を続けているとします。イメージではいつも通りに投げているつもりが、実際には肘がいつもより下がっているため外反ストレスがかかりやすい状態になっています。
もしくは、何となく肘が下がっている感じがするから「今日は意識的に肘を上げて投げよう」とするでしょう。そうういった意識の中で生まれる運動は、スムーズな動きを阻害し力みにつながるものです。
こういった動作の繰り返しで、肩や肘には繰り返されるストレスが増大して投球障害へとつながるリスクが増強するのです。そのリスクを最小限にするために「アームケア」的取り組みを選手自身が日々やる必要があるのです。
身体の再調整によるパフォーマンスレベルの維持・向上
アライメントの変化や筋出力の変化は僅かなものかもしれませんが、その僅かな左右差や通常時とのギャップは自身のパフォーマンスを低下させるだけの可能性を持っています。
先述したように、アライメントの影響で肘が上がりづらい状態で投球をすることはリリースポイントのズレや回転軸のズレを生みます。また、違和感を修正するために手先で修正をする必要が出てきます。もちろん、その修正を上手いことできる選手も中にはいますが、ほとんどがそうではありません。意図的に自分の肘の位置を変えたり、リリースポイントを修正するには「力み」や「いつもと違う身体の使い方」を生みます。
そのような状態で技術練習を繰り返すのは、本来自分が意図した動作とは異なる動作を繰り返すこととなります。結果としてパフォーマンスレベルは低下しやすい状況になると言えるでしょう。
パフォーマンスレベルを維持させる、もしくは少しでも向上させるためには、それ相応の身体状態で技術練習に臨む必要があるのです。そのためにも日々の「アームケア」を行うことが大切なのです。
アームケアをせずに野球することによるデメリット
長期離脱を余儀なくされるケースがある
ケアしない状態でプレーを続けることにより、ストレスが蓄積していきます。野球肩や野球肘の多くは機能的障害(組織の損傷を伴わない)が多いです。
繰り返されるストレスが同一箇所に集まることにより症状が発症する、ということです。つまり、日々のケアをしないことで野球肩や野球肘になるリスクが高くなるのです。その程度が軽度であれば復帰までに時間を要さないです。が、痛みが強く慢性化したケースにおいては復帰までに時間を要すケースが多いです。
また、力みやその日の感覚による修正でうまくパフォーマンスを発揮できない時に力を使うことでパフォーマンスを上げようとした時は外傷(一回の外力に組織が耐えられずに損傷する)リスクが高くなります。よくトミージョンなどで聞く、肘の内側の靭帯を損傷し手術となると復帰まで半年を要します。シーズンを棒に振ることになるのです。
力の発揮や身体の使い方が悪くなりパフォーマンスレベルが低下する
アライメントや可動性、筋出力が落ちた状態で練習に臨んでも思うような結果は出ません。本来自分が発揮出るはずの力が出ない状態で練習をしているので当たり前です。アームケアで自分自身の身体に向き合わなければ、そもそも現在の自分の状態を把握はできません。
機能が落ちた状態で練習に臨んだ結果、うまくいかない結果を修正しようとあれこれ形を変えようとするでしょう。そうすることで、非効率な使い方を繰り返して身体はその動きを学習してしまいます。非効率な動きを繰り返してもパフォーマンスは上がりません。むしろ下がる可能性が大きくなります。
まとめ
- アームケアとは、投球障害(野球肘や野球肩)のリスクを低減するために身体機能を調整すること
- 選手の全身も機能状態を把握する必要があり一人では困難なため、選手とトレーナーがペアで行う
- アームケアをすることで、疲労軽減や障害リスクの低減、パフォーマンスレベルの維持・向上が期待できる
- アームケアをしないことで、障害リスクの増大やパフォーマンスレベルの低下を引き起こす可能性がある
アームケアをすることによる恩恵はとても大きいです。そしてやらないことによる不利益が時には、長期離脱を余儀なくすることになります。
中学・高校野球の実働期間は、入学から夏の最後の大会まで2年4ヶ月ほどしかありません。ただでさえ短い期間を怪我で半年も無駄にするわけにはいかないのです。だからこそ今からでも、自分自身の身体と向き合う時間を作ってアームケアをする時間を作ってより良い野球ライフを送ろうじゃないですか!
やるかやらないかで差は大きく開きます。あなたの野球ライフがより良いものになりますように!