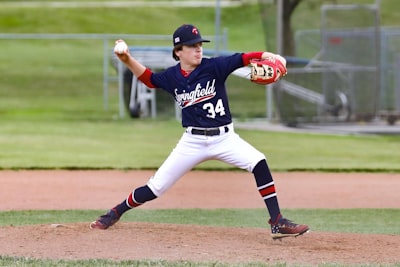野球– category –
-
野球の投球動作における「トップを作る」に対する考え
 今回は投球動作における「トップ」に対する私の意見をあれこれ述べたいと思います。なぜこの記事を書こうと思ったかというと、今に始まったことではありませんが「トップを作る」という言葉が逆にトップを崩すと思ったのがきっかけです。 というのも、私は理学療法士を始めた1年目から投球障害に向き合ってきました。私自身も小学生から野球を始め、現在に至るまで趣味程度ではありますが野球を続けています。私の周りの人も、リハビリで関わる人も投球障害に悩む人はたくさんいます。 その中で多くの人に共...
今回は投球動作における「トップ」に対する私の意見をあれこれ述べたいと思います。なぜこの記事を書こうと思ったかというと、今に始まったことではありませんが「トップを作る」という言葉が逆にトップを崩すと思ったのがきっかけです。 というのも、私は理学療法士を始めた1年目から投球障害に向き合ってきました。私自身も小学生から野球を始め、現在に至るまで趣味程度ではありますが野球を続けています。私の周りの人も、リハビリで関わる人も投球障害に悩む人はたくさんいます。 その中で多くの人に共... -
投球復帰をする上で優先すべきは「距離ではなく強さ」である!
 投球復帰に向けて頑張っている選手のなかで、競技現場やリハビリの際によく見受けられるのが「投球できる距離」を追い求めているケースです。そして、こういったケースはしばしば完全復帰に時間を要すように感じます。 大切なのは「出力をいかに10割に近づけれるか」だと私は考えます。 どれだけ距離を投げられても、それが山なりの投球では競技には通用しません。これが投手なら尚更です。100球以上の球をほぼ全力で投げ切らなければいけないのですから。 ただ、実際には キャッチボールである程度の距離...
投球復帰に向けて頑張っている選手のなかで、競技現場やリハビリの際によく見受けられるのが「投球できる距離」を追い求めているケースです。そして、こういったケースはしばしば完全復帰に時間を要すように感じます。 大切なのは「出力をいかに10割に近づけれるか」だと私は考えます。 どれだけ距離を投げられても、それが山なりの投球では競技には通用しません。これが投手なら尚更です。100球以上の球をほぼ全力で投げ切らなければいけないのですから。 ただ、実際には キャッチボールである程度の距離... -
【野球選手必見!】よく「腕のしなり」っていうけど、ちゃんとしなれてる?
 よく「腕がしなる」とか「肘がしなる」って言葉が一人歩きしてるな〜、と感じることが多いです。皆さんも一度は聞いたことがあると思います。 速い球を投げるため、遠くにボールを投げるには「しなりが必要だ!」なんて言葉、聞いたことありますよね?じゃあ、それってどこがしなってるんですか?どうすれば動きが改善し、適切なしなりができますか? そこまでを考えて動作改善に努めるのか、しなりを出すことだけにフォーカスしてブリッジをやり続けるのか、で得られる効果は全くの別物です。 加えて、し...
よく「腕がしなる」とか「肘がしなる」って言葉が一人歩きしてるな〜、と感じることが多いです。皆さんも一度は聞いたことがあると思います。 速い球を投げるため、遠くにボールを投げるには「しなりが必要だ!」なんて言葉、聞いたことありますよね?じゃあ、それってどこがしなってるんですか?どうすれば動きが改善し、適切なしなりができますか? そこまでを考えて動作改善に努めるのか、しなりを出すことだけにフォーカスしてブリッジをやり続けるのか、で得られる効果は全くの別物です。 加えて、し... -
野球パフォーマンス向上のためのトレーニング論を理学療法士・野球部トレーナー目線で語る
 ここ数年はSNSの発達でトレーニング方法や技術練習の動画がたくさん出回っています。元プロ野球選手や元甲子園出場経験のある人、理学療法士やアスレティックトレーナーなどなど、、。 特に、InstagramとTikTokは短時間動画で説明されているため、見やすく参考にしやすいと思います。 ただ、そのような動画を鵜呑みにしてはいけないと私は思います。 自分は動画を上げてないくせに何を言っている じゃあ、何をやればいいんだ なんて思われているのではないかと思います。 確かに、私自身は「パフォー...
ここ数年はSNSの発達でトレーニング方法や技術練習の動画がたくさん出回っています。元プロ野球選手や元甲子園出場経験のある人、理学療法士やアスレティックトレーナーなどなど、、。 特に、InstagramとTikTokは短時間動画で説明されているため、見やすく参考にしやすいと思います。 ただ、そのような動画を鵜呑みにしてはいけないと私は思います。 自分は動画を上げてないくせに何を言っている じゃあ、何をやればいいんだ なんて思われているのではないかと思います。 確かに、私自身は「パフォー... -
【野球選手の怪我予防をするために!】理学療法士・トレーナーが語る!試合や練習前後のコンディショニング戦略
 学生野球の指導者や選手の皆さん。こんなこと思っていませんか? 練習前や試合前のアップメニューをどう作成しようか、、 ケアは大事だというけど、自分で行う方法がわからない、、 日々の練習や試合になるべくベストな状態で望みたい! 私がトレーナーとして活動する現場や職場でよく聞く言葉ですので、もしかしたら役に立つかと思いこの記事を書くこととしました! 私はこの悩みを解決する方法は2つだと考えており、実際の現場指導で以下の2点を指導しています。 練習や試合前のアップメニューをルーティ...
学生野球の指導者や選手の皆さん。こんなこと思っていませんか? 練習前や試合前のアップメニューをどう作成しようか、、 ケアは大事だというけど、自分で行う方法がわからない、、 日々の練習や試合になるべくベストな状態で望みたい! 私がトレーナーとして活動する現場や職場でよく聞く言葉ですので、もしかしたら役に立つかと思いこの記事を書くこととしました! 私はこの悩みを解決する方法は2つだと考えており、実際の現場指導で以下の2点を指導しています。 練習や試合前のアップメニューをルーティ... -
【5分でわかる!】理学療法士が野球における「アームケア」を徹底解説!
 突然ですが、皆さんは「アームケア」という言葉を知っていますか。とは言う私もつい最近までは知りませんでした。長年野球部のトレーナー、理学療法士として働いてたのに恥ずかしい限りです、、 とはいえ、やっていること自体は同じことをやってきているので、自分自身がやっていることは間違ってはいないんだな、と再確認できたのは良かったです。 この「アームケア」はメジャーリーグや日本のプロ野球のなかでもメディカル系トレーナーなどが選手と一緒になって行っていたり、装着する測定器によりデータ...
突然ですが、皆さんは「アームケア」という言葉を知っていますか。とは言う私もつい最近までは知りませんでした。長年野球部のトレーナー、理学療法士として働いてたのに恥ずかしい限りです、、 とはいえ、やっていること自体は同じことをやってきているので、自分自身がやっていることは間違ってはいないんだな、と再確認できたのは良かったです。 この「アームケア」はメジャーリーグや日本のプロ野球のなかでもメディカル系トレーナーなどが選手と一緒になって行っていたり、装着する測定器によりデータ... -
正しい投球フォームとは何か。そんなものはない、自分の体力や技術で投球フォームは出来上がるものだ!
 一昔前までは、「正しい投球フォーム」なんていう概念はあまりなかったように感じます。 むしろ、形にこだわらずいかに早く投げるか、いかに遠くに投げるかだけを考えていたような。(田舎者の私だけでしょうか。笑) 最近は色んな解析装置などの発達で、数値や動作分析が目で見てわかるようになりました。また、そういった最新メカを使って動作指導をする施設も増えている印象です。 データは嘘をつかないかもしれません。実際に球速がどれくらいだ、回転数がどれくらいだ、回転軸がどうだ、とか。 け...
一昔前までは、「正しい投球フォーム」なんていう概念はあまりなかったように感じます。 むしろ、形にこだわらずいかに早く投げるか、いかに遠くに投げるかだけを考えていたような。(田舎者の私だけでしょうか。笑) 最近は色んな解析装置などの発達で、数値や動作分析が目で見てわかるようになりました。また、そういった最新メカを使って動作指導をする施設も増えている印象です。 データは嘘をつかないかもしれません。実際に球速がどれくらいだ、回転数がどれくらいだ、回転軸がどうだ、とか。 け... -
動きを真似ることによる経験値と身体負荷
 先日、クリニックにリハビリで通院している小学校高学年の野球選手A君とのやりとり。 私「投球開始時につま先が外側を向いているけど、そういうフォーム指導を受けているの?」 A君「Youtubeでこうすると球速が速くなるのをみたから」 こんな一幕がありました。 私なりの見解としては、①つま先を外に向けることで股関節外旋位を取りやすくなる⇨②ステップ時に軸足の股関節が外旋位になりやすい⇨③重心移動をする際に早期に荷重がステップ脚に乗るのを防ぐ⇨④上体の突っ込みを抑えて下半身からの力を伝達しやす...
先日、クリニックにリハビリで通院している小学校高学年の野球選手A君とのやりとり。 私「投球開始時につま先が外側を向いているけど、そういうフォーム指導を受けているの?」 A君「Youtubeでこうすると球速が速くなるのをみたから」 こんな一幕がありました。 私なりの見解としては、①つま先を外に向けることで股関節外旋位を取りやすくなる⇨②ステップ時に軸足の股関節が外旋位になりやすい⇨③重心移動をする際に早期に荷重がステップ脚に乗るのを防ぐ⇨④上体の突っ込みを抑えて下半身からの力を伝達しやす... -
野球に必要な柔軟性
 これまで2回にわたり柔軟性に関連する記事を書きました。今回は、実際に野球選手において私が必要と考える柔軟性の項目を挙げてみたいともいます。 野球に必要な柔軟性 上半身編 大胸筋、小胸筋 どちらも胸の前面につく筋肉です。作用は異なりますが、筋肉が硬くなることによりすくみ肩になりやすくなります。 結果として、投球時に十分な可動域が出なくなってしうため怪我のリスクや出力の低下を伴います。 大円筋、小円筋 肩甲骨から上腕骨に走行する筋肉です。 筋肉が伸びづらくなることにより、肩...
これまで2回にわたり柔軟性に関連する記事を書きました。今回は、実際に野球選手において私が必要と考える柔軟性の項目を挙げてみたいともいます。 野球に必要な柔軟性 上半身編 大胸筋、小胸筋 どちらも胸の前面につく筋肉です。作用は異なりますが、筋肉が硬くなることによりすくみ肩になりやすくなります。 結果として、投球時に十分な可動域が出なくなってしうため怪我のリスクや出力の低下を伴います。 大円筋、小円筋 肩甲骨から上腕骨に走行する筋肉です。 筋肉が伸びづらくなることにより、肩... -
運動に必要な身体づくりをするための柔らかさ
 前回の記事ではなぜ柔軟性を求めるかについてを書きました。ちなみにこんな感じ👇 じゃあ、どうやって柔軟性を獲得しようかということや、獲得した柔軟性をどう反映させるのかなどなど 色々な疑問が出てくる人、よくわからないけどとりあえず柔軟性あげておこうかなという人もいると思います。 今回は「柔らかさ」をどう獲得するかについて、あれこれぼやきたいと思います。 柔らかさをどう捉えるか じゃあそもそも、柔らかさって何なのかです。 私の中では柔らかさを考える際に大きく分けて2つと捉え...
前回の記事ではなぜ柔軟性を求めるかについてを書きました。ちなみにこんな感じ👇 じゃあ、どうやって柔軟性を獲得しようかということや、獲得した柔軟性をどう反映させるのかなどなど 色々な疑問が出てくる人、よくわからないけどとりあえず柔軟性あげておこうかなという人もいると思います。 今回は「柔らかさ」をどう獲得するかについて、あれこれぼやきたいと思います。 柔らかさをどう捉えるか じゃあそもそも、柔らかさって何なのかです。 私の中では柔らかさを考える際に大きく分けて2つと捉え...
12