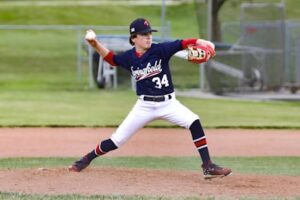投球復帰に向けて頑張っている選手のなかで、競技現場やリハビリの際によく見受けられるのが「投球できる距離」を追い求めているケースです。そして、こういったケースはしばしば完全復帰に時間を要すように感じます。
大切なのは「出力をいかに10割に近づけれるか」だと私は考えます。
どれだけ距離を投げられても、それが山なりの投球では競技には通用しません。これが投手なら尚更です。100球以上の球をほぼ全力で投げ切らなければいけないのですから。
ただ、実際には
- キャッチボールである程度の距離を投げなけらばいけない
- 外野からの返球でホームまで投げなければいけない
などの状況から、全体メニューに参加するために投げられる距離を伸ばすことを優先しなければいけない、と感じる選手が多いようです。
今回は、競技復帰に向けてどうプランニングするか、どう段階的に強度を上げていくか、そこに至るまでに何を考えるかをあれこれぼやいていきます。
なるべく投球休止期間を短くする
まず一番に考えるのは、投球休止期間を最小限にとどめることです。言い換えれば「早い段階で痛くない距離で、なるべく強く腕を振れるようにしていく」ということです。
投球休止期間が長くなることにより、投球感覚や投球に必要な肩周りの筋肉は低下します。また、学童期においては野球そのものに対するモチベーションの低下により、競技から離脱してしまうケースもあります。
投球休止期間を最低限に抑え、身体の機能低下を抑えることを目的とします。じゃあ、投球休止中もトレーニングやストレッチを継続して筋力や可動域が下がらないようにすればいいじゃないかという意見が出ると思います。
もちろん、そういう取り組みは行います。ただ、投げるための身体の使い方や筋発揮のタイミングは投げる中でしか養われません。だからこそ、投げられない時間を最小限にしたいのです!
ただ、上腕骨小頭離断性骨軟骨炎や肘頭疲労骨折、右肘内側側副靱帯損傷の術後などのケースおいては長期的な投球休止を要するものもあるため、Dr.との相談も必要です。
大会までの時間と選手の立ち位置
競技復帰へのプランをたてる上で「大会までの期間と選手の立ち位置」が非常に重要になると考えます。
大会までの期間が短く、ベンチ入りを争う立場にいる選手であれば少し無理をしてでも、急いで復帰に向かう必要があります。逆にレギュラーやエースの立場が確約されている選手であれば、無理をせずに確実に大会期間までの間を治療に専念させることができます。
そのため、一番最初に考えるのが「大会までの期間と選手の立ち位置」になるのです。もちろん、無理をするケースにおいてはDrと相談の上、予後として何が考えられるかを選手と保護者、指導者に説明した上で進めていく必要があります。
短い距離かつネットに向かっていかに強く投げられるかの距離を伸ばす
復帰に向けて段階的に強度をあげていく中で優先することは、近い距離を強く投げることです。実践での投球強度と程遠い力で、どんなに遠投しても復帰にはつながりません。
コントロールを気にすると力みや、手先での調整に意識が向きスムーズな投球動作を阻害する要素となります。そのため、投げ始めはコントロールを気にしなくてもいいように壁あて・ネットスローを選択させます。
距離は5mほど、球数50球をスタートに設定し、痛みの有無を確認しながら出力を上げていきます。何度も言いますが「大事なのは距離よりも力強く投げられるか」です。強く投げられる距離を徐々に伸ばしていきます。最終目標は塁間+10mほどを10割で投げられるか、5mネットスローを10割で100球投げられるかとしています。
満足に復帰できていない選手、復帰が長引いている選手はこの目標を達成できていないケースがほとんどです。もちろん、ただ投げればいいわけではなく、機能不全を改善しているのが必須条件ですが。